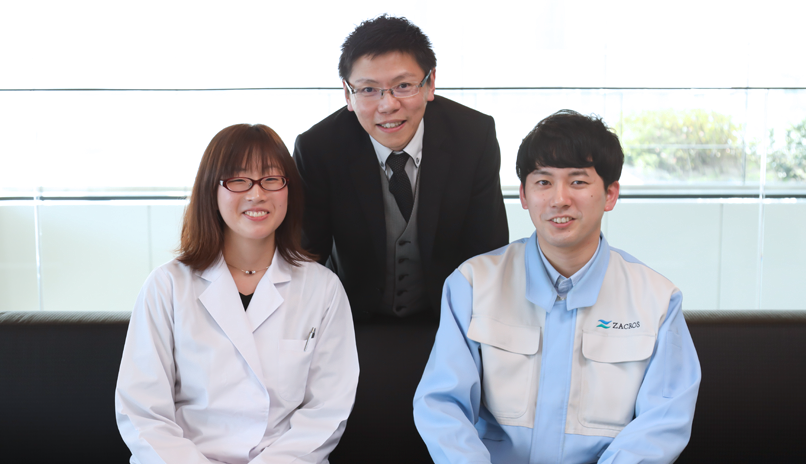手作業から装置による
大量培養へ
iPS細胞による
再生医療を強力に推進
左)株式会社日立製作所 研究開発グループ
基礎研究センタ 日立神戸ラボ研究員 斉藤 洸氏
右)大日本住友製薬株式会社 再生・細胞医薬神戸センター
ティッシュエンジニアリンググループ主席研究員 関谷 明香氏
Interview 2020年2月
平素より当サイトをご利用いただき、誠にありがとうございます。
2025年3月末をもちまして、当サイトはアーカイブ情報として公開させていただいております。
なお、神戸医療産業都市内における様々な取り組みについては、
引き続き以下のページでご覧いただけます。
https://www.fbri-kobe.org/cluster/kbic-unei/
STORY 01
iPS細胞自動培養装置の開発
「もう私が鳩山に行くしかないのかな」
2016年、iPS細胞の自動培養評価試験が難航するなか、大日本住友製薬の関谷明香主席研究員は、埼玉県鳩山町にある日立製作所・基礎研究センタに自ら赴く覚悟を決めようとしていました。同センタこそは、2002年から日立が細胞の閉鎖系自動培養装置開発に取り組んできた拠点です。
大日本住友製薬が京都大学と共同で、iPS細胞を使った再生医療の研究に着手したのが2014年のこと。翌2015年からは日立を交えた3者による、iPS細胞の大量培養装置の実用化に向けた取り組みが始まっています。
iPS細胞を使った再生医療の普及には、細胞の大量培養が欠かせません。熟練者が手作業で培養するのと同等レベルの品質を保ちながら、いかにiPS細胞を大量に培養できるか。そのカギを握るのが自動培養装置です。

STORY 02
立ちふさがる距離の壁
治療のターゲットはパーキンソン病であり、ドパミンを出す神経細胞をiPS細胞から作って移植します。この治療法の有効性は、サルを使った京都大学・iPS細胞研究所の髙橋淳教授の研究により既に検証済みでした。ただしヒトに移植するには、iPS細胞が10億個単位で必要となります。
「当社は以前から細胞培養装置の研究を進めており、密閉容器を活用した閉鎖系の自動培養装置の試作機は開発済みでした。共同開発では当初、その装置を使ってiPS細胞の培養に取り組んだのです。大日本住友製薬さんとは何度もミーティングを行い、もちろんメールも頻繁にやり取りしていました。とはいえ埼玉と神戸の距離はいかんともしがたく、開発はなかなか思うように進みませんでした」と、日立製作所研究開発グループの斉藤洸氏は開発当初のもどかしい状況を振り返ります。

手作業による細胞培養を機械化に置き換えると、何が変わるのか。まず培養面積に関して直径3cm程度のシャーレで行っていた作業を、一気に50倍ぐらいの面積で行うようになります。
「サイズがこれほど大きくなると、同じ細胞培養とはいえ、以前とは見えてくる風景が変わってしまうのです。例えばシャーレなら容器が少々歪んでいたとしても、大した問題にはなりません。けれどもこれが大きな容器となると、その歪みによって培養液が均等に行き渡らなくなったりします。だから実験レベルとはものの見方、考え方を改めないと単純に機械化してもうまくいかない。そこで装置開発のプロとの共同作業が必須となるわけです。ところが、一緒に作業するには一日がかりで埼玉まで行かなければならない。何とか状況を変えなければと思っていた矢先に、日立さんが神戸に来てくれることになりました。今から思い返せば、これが開発の本格的なスタートだったのかもしれません」(関谷氏)
STORY 03
距離の近さが開発を急加速
2017年、日立は神戸医療産業都市に日立神戸ラボを開設しました。その場所は、大日本住友製薬の研究所から徒歩で10分の近さ。培養装置の試作機は、大日本住友製薬の研究所内に設置されました。
「漠然と開発にはずみがつくだろうな、とは思っていました。トラブルシューティングへの対応も早くなるだろうし、メールでは伝わらない細かなニュアンスも、面と向かって話し合えばダイレクトに伝わりますから」(関谷氏)

ところが、実際には想像を遥かに超える効果があったのです。京都大学の髙橋教授が作成した細胞培養に関するプロトコルは、もちろん両者が共有していました。ただ、そのプロトコルに記されていたのはあくまでラボスケールでの条件であり、装置を使う大きなスケールになると条件を見直す必要があります。
そのような見直し作業を同じラボ内で行うメリットについて関谷氏は「メンテナンス作業を後ろから見ていて装置の感覚を共有できた」と語り、斉藤氏も「手作業での培養風景を目の当たりにしたおかげで、装置に追加すべき機能が明らかになった」と場所と時間を共有する成果を強調します。
お互いが同じ空間で、同じ光景を目にしながら、顔を合わせて語り合う。メールの文言では伝えきれないニュアンスや、たとえ写真を撮っても写しきれない微妙な現場感覚を、お互いが同じレベルで理解できるのです。
その成果を「当社の研究所内に設置された装置を使って初めて細胞培養し、結果が出た時点で、従来の手作業による培養とは明らかに様相が異なっていると感じました。それこそ一つ抜けた感覚がありましたね」と関谷氏は評価します。これ以降、研究開発に弾みがつきました。

STORY 04
細胞/研究開発にとって最高の環境
iPS細胞は生き物だから、その生育に適した環境要件があります。従来の手作業による培養では、いかに熟練者が高度な手技を駆使したとしても、ばらつきを完全にゼロにはできません。例えば温度変動や雑菌の混入など、細胞にとって好ましくない状態が起こり得たのです。
これに対して密閉型の自動培養装置の中であれば、細胞にとって最高の環境が維持されます。つまりiPS細胞の培養には、人工的な環境の方が望ましいのです。ただ完全に自動化に移行するには、まだ課題が残されています。培養を終えた細胞を、培養容器からスムーズにはがすプロセスです。この工程を自動化できれば、理想的な培養装置が誕生するはずです。
「まずは手作業を機械に置き換えてみました。その結果を判断し、機械が得意なこと、機械にしかできないこと、人間が得意なこと、人間にしかできないことを切り分けて開発を進めてきました」と、関谷氏はこれまでの経緯を振り返ります。
「モニタリングで得た結果をフィードバックして環境改善に努めています。ヒントは培養液にあるようです。さらに今後はAIを活用した画像解析により、良い細胞と悪い細胞を見極められるようにしたい」と抱負を語る斉藤氏。
装置開発の過程では、日立にはない技術を持つ企業を神戸医療産業推進機構から紹介されたケースもあります。神戸医療産業都市では、再生医療に関する勉強会が開催され、最先端の知識を得る機会も豊富に用意されています。この環境について関谷氏は「細胞が培養に関して人工的な最高の環境を好むように、私もこの人工島を研究開発に関する理想的な環境と受け止めています」と締めくくってくれました。
※当研究開発は、国立研究開発法人日本医療研究開発機構(AMED)の「再生医療の産業化に向けた評価基盤技術開発事業」において実施されました。
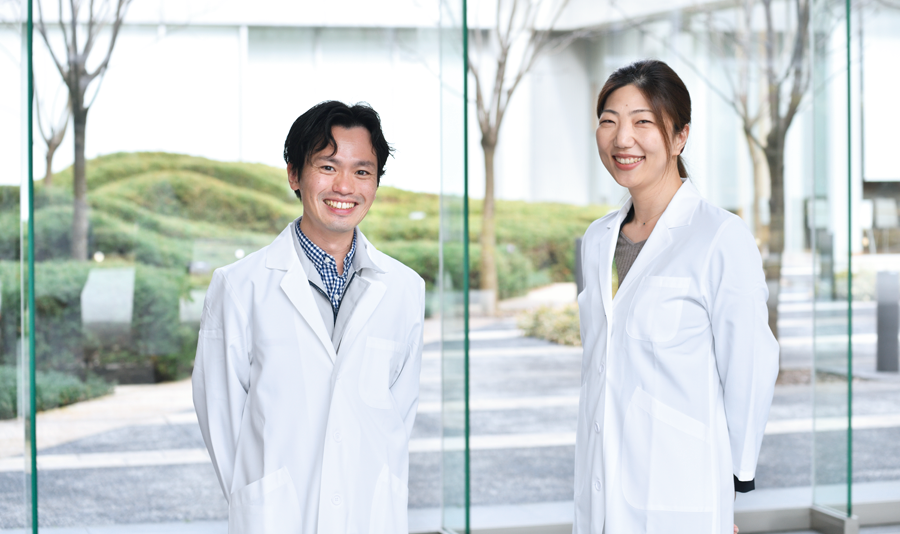
そのほかの記事
OTHER CASE